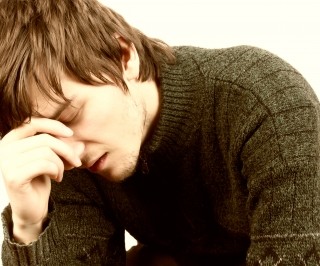【発達障害の対応】整理整頓や片付けができない、対処法や対策は?
ADHDなど発達障害がある子どもの中には、整理整頓したり、部屋を片付けることが苦手な傾向があります。
部屋の片付けができず、散らかったままになっていると、物をなくしやすくなりますし、気が散りやすく、宿題など勉強にも集中できなくなってしまいます。
スポンサーリンク
発達障害だと片付けができない?
ADHDなど発達障害の場合、使ったものを元の場所に戻すことが苦手な傾向があります。
不注意や忘れやすい特性のため、別のことに気をとられて片付けることを忘れてしまうのです。また、出して使ったものを片付けようと思っても、どこに片付ければいいのかわからなくなってしまうこともあります。
そのため、発達障害の子どもの部屋や机などが整理整頓できず、散らかったままの状態で、必要なものが探せなくなってしまう事態に陥ってしまいます。
部屋が散らかりすぎると、片付けること自体が面倒臭くなってしまい、さらに物で溢れて散乱してしまうことになりかねません。
このような状態の中で、発達障害の子どもに親が「片付けなさい」「きちんと整理整頓しなさい」と注意したところで、自分で部屋を片付けることはかなり困難といえます。
整理整頓できない発達障害【親の対応】
自分ひとりでは、うまく部屋を片付けたり、物を整理整頓できない発達障害の子どもの対応として、まず最初は親が一緒に片付けを手伝うようにしましょう。
親に手伝ってもらうだけで、発達障害の子どもは片付けに取り組みやすくなるものです。そして、徐々に親の手助けを減らし、最終的には発達障害の子どもひとりで片付けや整理整頓ができるようにしてきます。
スポンサーリンク
また、発達障害の片付け対策として「散らかる前に片付けること」も重要なポイントです。
足の踏み場もないほどに散らかってしまっていては、いざ片付けようとなっても、時間労力がかかってしまい、片付けることにおっくうになってしまいます。
親の対応として、散らかる前に定期的に片付けるように声かけをすることも大切です。
片付けができたら「部屋がきれいになって気持ちいいね」などの声かけで、整理整頓できている状態の部屋は居心地がよいということを実感させることも大切です。また、上手に片付けできたことをきちんとほめてあげることも忘れないようにしましょう。
整理整頓&片付けの対策は?
発達障害の子どもの中には、使ったものをどこに片付ければいいかわからなくなり、そのままになってしまい、片付けや整理整頓ができない、というケースもあります。
そういう場合には、物を置く場所、片付ける場所を決めておき、そこに絵や文字などでマークをつけておきましょう。直す物の写真を貼っておく、という対策も有効です。
引き出しやタンスの中は、仕切りをつくり、物を個別に片付けることができるようにすると、発達障害の子どもも整理整頓がしやすくなります。
引き出しの中のスペースが広すぎると、物を放り込んだままの状態になってしまいやすく、仕切り板や小箱などを使って区分けするとよいでしょう。
ただし、あまりに細かく物の置き場所を決めすぎてしまうと、片付ける行為自体の負担が大きくなってしまいます。片付けよう、整理整頓しよう、という意欲が失われてしまっては元も子もありません。
おもちゃは全部おもちゃ箱に入れればいい、など、ひとつひとつの置き場所まで細かく決めすぎないようにしましょう。
◆この記事は、お茶の水女子大学大学院教授である榊原洋一先生執筆・監修「図解よくわかる発達障害の子どもたち(ナツメ社)」の内容に基づいて、当サイト運営事務局の心理カウンセラーが記事編集をしています。
スポンサーリンク